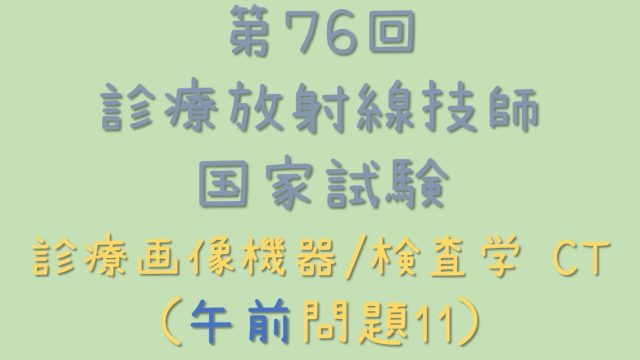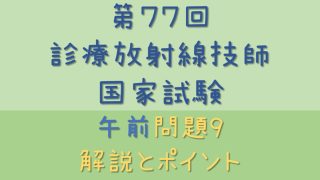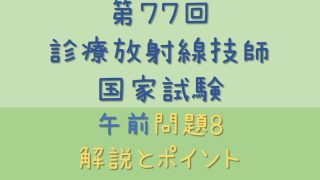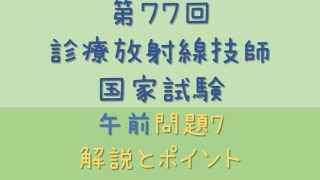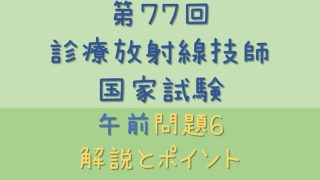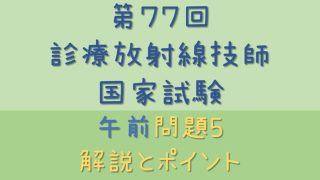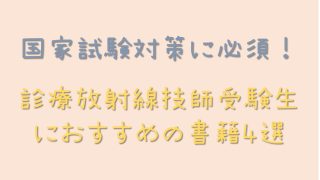午後/問題1
細胞内でATPを産生するのはどれか。
1.核小体
2.ゴルジ体
3.リボゾーム
4.リソソーム
5.ミトコンドリア
午後/問題2
細胞膜の層構造を形成する主成分はどれか。
1.糖 質
2.無機質
3.蛋白質
4.リン脂質
5.コラーゲン
午後/問題3
DNA合成期はどれか。
1.G0期
2.G1期
3.G2期
4.M期
5.S期
午後/問題4
抗体を産生する形質細胞に分化するのはどれか。
1.好酸球
2.好中球
3.B細胞
4.T細胞
5.マクロファージ
午後/問題5
健常成人で動脈血が流れるのはどれか。2つ選べ。
1.奇静脈
2.肺静脈
3.肺動脈
4.上大静脈
5.気管支動脈
午後/問題6
腹腔動脈から直接分岐するのはどれか。
1.右胃動脈
2.左胃動脈
3.短胃動脈
4.右胃大網動脈
5.左胃大網動脈
午後/問題7
健常人で最も前方(腹側)に位置するのはどれか。
1.右心房
2.右心室
3.左心房
4.左心室
5.上行大動脈
午後/問題8
機能血管と栄養血管とが異なるのはどれか。2つ選べ。
1.肺
2.肝臓
3.脾臓
4.腎臓
5.膵臓
午後/問題9
後腹膜腔に存在するのはどれか。2つ選べ。
1.空腸
2.上行結腸
3.横行結腸
4.下行結腸
5.S状結腸
午後/問題10
腎臓の機能でないのはどれか。
1.血圧の調節
2.体温の維持
3.老廃物の排出
4.体液量の調節
5.酸塩基平衡の調節
午後/問題11
大脳基底核に含まれるのはどれか。2つ選べ。
1.海馬
2.視床
3.内包
4.淡蒼球
5.尾状核
午後/問題12
眼球運動に関わるのはどれか。
1.視神経
2.滑車神経
3.顔面神経
4.三叉神経
5.迷走神経
午後/問題13
血糖値を上昇させるのはどれか。
1.インスリン
2.ガストリン
3.グルカゴン
4.プロラクチン
5.アルドステロン
午後/問題14
感染症でないのはどれか。
1.淋病
2.破傷風
3.帯状疱疹
4.多発性筋炎
5.流行性耳下腺炎
午後/問題15
Ⅳ型アレルギー反応(遅延型、細胞性免疫型)はどれか。
1.気管支喘息
2.不適合輸血
3.アトピー性皮膚炎
4.アナフィラキシー
5.ツベルクリン反応
午後/問題16
扁平上皮癌の頻度が高いのはどれか。
1.胃癌
2.膵癌
3.乳癌
4.食道癌
5.大腸癌
午後/問題17
肺塞栓症の危険因子はどれか。
1.肺炎
2.貧血
3.心房細動
4.長期臥床
5.アスベスト曝露
午後/問題18
サルコイドーシスの発生頻度が最も高いのはどれか。
1.脳
2.甲状腺
3.肺
4.胃
5.腎臓
午後/問題19
我が国の肝硬変の原因で最も多いのはどれか。
1.A型肝炎
2.B型肝炎
3.C型肝炎
4.薬剤性肝炎
5.アルコール性肝炎
午後/問題20
膵臓の外分泌酵素はどれか。2つ選べ。
1.リパーゼ
2.アミラーゼ
3.インスリン
4.グルカゴン
5.クレアチニン
午後/問題20
膵臓の外分泌酵素はどれか。つ選べ。
1.リパーゼ
2.アミラーゼ
3.インスリン
4.グルカゴン
5.クレアチニン
午後/問題21
子宮頸癌の腫瘍マーカーはどれか。
1.AFP
2.HCG
3.NSE
4.PSA
5.SCC
午後/問題22
透析が導入される患者の原疾患で最も多いのはどれか。
1.痛風腎
2.腎硬化症
3.腎細胞癌
4.糖尿病腎症
5.慢性糸球体腎炎
午後/問題23
くも膜下出血の原因で最も多いのはどれか。
1.脳炎
2.脳梗塞
3.脳腫瘍
4.脳動脈瘤
5.脳内血腫
午後/問題24
高血圧をきたさないのはどれか。
1.褐色細胞腫
2.インスリノーマ
3.クッシング症候群
4.甲状腺機能亢進症
5.原発性アルドステロン症
午後/問題25
IVRに該当しないのはどれか。
1.胃瘻造設術
2.肝動脈塞栓術
3.腸骨動脈形成術
4.画像誘導放射線治療
5.経皮的エタノール注入療法
午後/問題26
緩和治療でないのはどれか。
1.根治手術
2.精神的ケア
3.褥瘡予防処置
4.医療用麻薬による痛み管理
5.放射線治療による痛み管理
午後/問題27
平成22年簡易生命表で我が国の男性の平均寿命に最も近いのはどれか。
1.72年
2.74年
3.76年
4.78年
5.80年
午後/問題28
感染症が成立するには、感染源の存在、感染経路の存在および宿主の感受性という条件が必要である。
宿主の感受性に対する予防対策はどれか。
1.入国時の検疫
2.麻疹患者の隔離
3.インフルエンザワクチンの接種
4.HIV感染妊婦に対する帝王切開
5.血液製剤の検査による汚染血液の排除
午後/問題29
生活習慣病はどれか。2つ選べ。
1.結核
2.糖尿病
3.脳梗塞
4.バセドウ病
5.潰瘍性大腸炎
午後/問題30
ヨード造影剤の副作用で頻度が最も低いのはどれか。
1.悪心
2.蕁麻疹
3.背部痛
4.顔面蒼白
5.呼吸困難
午後/問題31
γ線によるDNA損傷で正しいのはどれか。
1.本鎖切断は修復されない。
2.DNA損傷はγ線に特異的である。
3.本鎖切断は二本鎖切断よりも多い。
4.本鎖切断は細胞死の直接原因である。
5.DNA損傷の修復は照射後約時間で完了する。
午後/問題32
X線に対する反応のα/βが最も小さいのはどれか。
1.脱毛
2.下痢
3.脊髄症
4.口内炎
5.湿性落屑
午後/問題33
放射線の全身被ばくによる晩発障害はどれか。
1.脱毛
2.下痢
3.皮膚炎
4.急性白血病
5.白血球減少
午後/問題34
胸部の放射線治療による合併症のうち確率的影響はどれか。
1.乳癌
2.肺炎
3.不妊
4.皮膚炎
5.心血管障害
午後/問題35
放射線の影響で正しいのはどれか。
1.遺伝的影響は確定的影響である。
2.早期障害では確率的影響はない。
3.確率的影響の重篤度は線量に依存する。
4.確率的影響の代表的疾患に白内障がある。
5.固形癌発生までの潜伏期間は白血病よりも短い。
午後/問題36
放射線によるがんの発生率に関して、低線量域における「しきい値なし仮説」を説明した図として正しいのはどれか。
ただし、※はがんの自然発生レベルを示す。

午後/問題37
放射線感受性の順序で正しいのはどれか。
高い → 低い
1.骨 > 脊髄 > 肺
2.脊髄 > 骨 > 肺
3.脊髄 > 肺 > 骨
4.肺 > 脊髄 > 骨
5.肺 > 骨 > 脊髄
午後/問題38
放射線感受性が低いのはどれか。
1.食道癌
2.喉頭癌
3.悪性黒色腫
4.非小細胞肺癌
5.悪性リンパ腫
午後/問題39
OERが大きいのはどれか。
1.α線
2.γ線
3.炭素線
4.ネオン線
5.中性子線
午後/問題40
分割照射を行った際、血管周囲の細胞が先に死滅し、照射回数が進むにつれて外側部分の腫瘍細胞が次に死滅していく現象はどれか。
1.再増殖
2.再分布
3.再酸素化
4.亜致死障害からの回復
5.潜在的致死障害からの回復
午後/問題41
間接電離放射線はどれか。2つ選べ。
1.炭素線
2.電子線
3.陽子線
4.中性子線
5.特性X線
午後/問題42
正しいのはどれか。
1.原子番号は陽子数と等しい。
2.鉛の同位体は3種類である。
3.M殻の最大電子数は10個である。
4.中性子の質量は陽子よりも小さい。
5.天然に存在する元素は106種類である。
午後/問題43
下式の反応で生じるエネルギーQ(MeV)はどれか。
7Li+1H→4He+4He+Q
ただし、各質量数は以下の通りとする。1H:1.0073u、4He:4.0026u、7Li:7.0160u、1u = 932 MeV
1.13
2.17
3.21
4.25
5.29
午後/問題44
半減期29年の90Srは、分岐比で半減期64時間の90Yに壊変する。
40 GBqの90Srが58年経過したとき、90Yの放射能(GBq)はどれか。
1.0
2.5
3.10
4.20
5.40
午後/問題45
特性X線に関係するのはどれか。
1.クラマースの式
2.メスバウアー効果
3.モーズレーの法則
4.デュエン・ハントの法則
5.ガイガー・ヌッタルの法則
午後/問題46
30keV光子が水に入射した場合の相互作用はどれか。2つ選べ。
1.光電吸収
2.光核反応
3.三対子生成
4.電子対生成
5.コンプトン散乱
午後/問題47
電子と物質の相互作用で正しいのはどれか。
1.原子番号が大きいほど弾性散乱は小さい。
2.エネルギーが大きいほど弾性散乱は大きい。
3.原子番号が大きいほど質量衝突阻止能は大きい。
4.原子番号が大きいほど質量放射阻止能は大きい。
5.エネルギーが大きいほど質量放射阻止能は小さい。
午後/問題48
中性子で正しいのはどれか。
1.速中性子の遮へいには鉛が有効である。
2.γ,n反応にしきいエネルギーはない。
3.熱中性子で10B(n, α)7Li反応が生じる。
4.β–壊変で陽子と反ニュートリノを放出する。
5.アップクォーク2個とダウンクォーク1個で構成されている。
午後/問題49
音響インピーダンスに影響を与えるのはどれか。2つ選べ。
1.音圧
2.音速
3.周波数
4.媒質の体積
5.媒質の密度
午後/問題50
Hounsfield値(CT値)を求める式はどれか。
ただし、μt、μwおよびμaはそれぞれ組織、水、および空気の線減弱係数とする。
午後/問題51
光電子増倍管の電極に10個の電子が入射すると、1段の電極で5個の二次電子が発生するとき、10段の電極で得られる電子の数はどれか。
1.20
2.100
3.512
4.1024
5.2048
午後/問題52
抵抗率2.66×10-8Ωmの導線がある。
断面積が1mm²、長さが500mであるときの抵抗(Ω)はどれか。
1.6.65
2.6.65×10-1
3.1.06×10-2
4.6.65×10-3
5.1.06×10-4
午後/問題53
図の回路に10分間通電したところ、36kJのエネルギーを消費した。
使用した抵抗R(Ω)とリアクタンスX(Ω)はどれか。
1.30, 40
2.40, 60
3.60, 80
4.80, 100
5.100, 120
午後/問題54
0.5μFのコンデンサ式X線装置を90kVに充電した後、15mAs放電したときの波尾切断電圧(kV)はどれか。
1.20
2.30
3.40
4.50
5.60
午後/問題55
人体に電流を1秒通電したとき、マクロショックの電流値で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.10μA以下の電流は安全である。
2.1mAの電流は最小感知電流である。
3.30mAの電流は離脱できる電流である。
4.50mAの電流は最大許容電流である。
5.1A以上の電流は火傷を生じる。
午後/問題56
pn接合ダイオードで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.直流を交流に変換する。
2.整流作用によって双方向に電流が流れる。
3.ツェナーダイオードは逆方向で電流が一定になることを利用する。
4.フォトダイオードでは接合部に光を当てたときのみ整流作用を行う。
5.逆方向バイアスではp型にマイナスの、n型にプラスの電圧を加える。
午後/問題57
演算増幅回路を図に示す。入力電圧が-1Vのとき、出力電圧Vo(V)はどれか。

1.0.015
2.0.15
3.1.5
4.15
5.150
午後/問題58
単位としてGyを用いるのはどれか。2つ選べ。
1.エネルギーフルエンス
2.カーマ
3.吸収線量
4.実効線量
5.照射線量
午後/問題59
カーマを求める際、エネルギーフルエンスに乗じる相互作用係数はどれか。
1.質量減弱係数
2.質量衝突阻止能
3.質量放射阻止能
4.質量エネルギー吸収係数
5.質量エネルギー転移係数
午後/問題60
放射線検出器に関する組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.電離箱 ― シンチレーション
2.CR-39 ― 黒化度
3.NaI(Tl) ― 潮解性
4.GM計数管 ― 電子なだれ
5.蛍光ガラス線量計 ― グロー曲線
午後/問題61
ファーマ形電離箱線量計を用いた診断用X線の線量測定で正しいのはどれか。
1.温度気圧補正が必要である。
2.極性効果補正が必要である。
3.照射野は線量計の幅に合わせて絞る。
4.電離容積の小さいものは使用できない。
5.線量計にビルドアップキャップを装着して測定する。
午後/問題62
GM計数管で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.β線の検出が可能である。
2.放射線エネルギーの分析が可能である。
3.分解時間内に入射してきた放射線が計数される。
4.出力パルスの大きさは一次イオン対数に比例する。
5.連続放電を停止させるために、クエンチングガスを用いる。
午後/問題63
電離箱線量計の一般再結合損失に影響を与えないのはどれか。
1.LET
2.印加電圧
3.電極間隔
4.中心電極の半径
5.外側電極の半径
午後/問題64
放射線の電離作用を直接利用するのはどれか。
1.Ge半導体検出器
2.金箔しきい検出器
3.蛍光ガラス線量計
4.チェレンコフ検出器
5.CsI(Tl)シンチレーション検出器
午後/問題65
NaI(Tl)のホールボディカウンタで測定できるのはどれか。
1.実効線量
2.甲状腺等価線量
3.体内のγ線放出核種の放射能
4.体内の純β放出核種の放射能
5.体内に存在する放射性物質からのα線スペクトル
午後/問題66
端窓形GM計数管によるβ線源の放射能測定の配置を図に示す。
線源から入射窓を見込む立体角Ωがπ/5ステラジアン、正味の計数率が100cpsであるときのβ線源の放射能(Bq)はどれか。
ただし、線源はβ線を100%放出し、線源による自己吸収は無視できる。また、GM計数管のβ線に対する検出効率を1とする。

1.100
2.159
3.500
4.1570
5.2000
午後/問題67
88Yのγ線スペクトルを図に示す。正しいのはどれか。

1.Aはシングルエスケープピークである。
2.Bはダブルエスケープピークである。
3.Cは後方散乱ピークである。
4.コンプトン端は見られない。
5.511keVのピークは898keV光子によって生じた陽電子の消滅γ線を示す。
午後/問題68
診療放射線技師が実施できる業務内容はどれか。
1.麻酔薬を投与する。
2.造影剤の選択を行う。
3.注射針を静脈に刺入する。
4.ゾンデを胃内に挿入する。
5.患者にX線検査に関する説明を行う。
午後/問題69
X線CT撮影で発生するおそれがあるのはどれか。
1.放射線肺炎
2.赤血球の減少
3.騒音による聴力障害
4.脳動脈クリップの逸脱
5.心臓ペースメーカの誤作動
午後/問題70
X線写真の鮮鋭度が向上するのはどれか。
1.撮影時間を長くする。
2.撮影距離を短くする。
3.感光材料の粒子径を大きくする。
4.被写体-検出器間距離を短くする。
5.X線管焦点を小焦点から大焦点にする。
午後/問題71
体表ポイントと脊柱の位置の組合せで正しいのはどれか。
1.喉頭隆起 ― 第3頸椎レベル
2.胸骨角 ― 第5頸椎レベル
3.剣状突起 ― 第9胸椎レベル
4.腸骨稜 ― 第4腰椎レベル
5.恥骨結合上縁 ― 仙骨レベル
午後/問題72
OMラインの定義はどれか。
1.外耳孔中心と外眼角を結ぶ線
2.両側の乳様突起下縁を結ぶ線
3.外耳孔上縁と眼窩下縁を結ぶ線
4.大後頭孔後縁と硬口蓋後縁を結ぶ線
5.硬口蓋後縁と後頭骨の最低点を結ぶ線
午後/問題73
胸部立位X線写真を後前方向で撮影する理由はどれか。
1.気管分岐部を描出する。
2.生殖腺の被ばくを軽減する。
3.グリッドのしま目を除去する。
4.心臓陰影の拡大率を小さくする。
5.ホルツクネヒト腔を描出する。
午後/問題74
成人の胸部立位X線撮影で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.低電圧で撮影する。
2.撮影前に隆椎の位置を確認する。
3.モリブデンフィルタを使用する。
4.撮影距離を150〜200cmに設定する。
5.肺野濃度が2.0以上になるように撮影条件を設定する。
午後/問題75
腹部X線写真を呼気で撮影する目的はどれか。
1.可検領域の拡大
2.腹部血管の描出
3.X線管の負荷軽減
4.腸管内ガスの排出
5.クロスオーバー効果の抑制
午後/問題76
左側臥位腹部正面X線撮影が診断に最も有用なのはどれか。
1.腎結石
2.急性膵炎
3.慢性胃炎
4.消化管穿孔
5.腹部大動脈瘤
午後/問題77
膝関節の撮影法はどれか。
1.レーゼ法
2.ストライカー法
3.ステンバース法
4.ローゼンバーグ法
5.コールドウェル法
午後/問題78
乳房X線写真を別に示す。正しいのはどれか。
1.C-C方向の撮影である。
2.脂肪性乳房の画像である。
3.大胸筋が描出されている。
4.拡大スポット撮影像である。
5.乳房下軟部組織が描出されていない。

午後/問題79
X線管に照射筒を装着するのはどれか。
1.歯科撮影
2.頸椎撮影
3.胸椎撮影
4.腰椎撮影
5.手指骨撮影
午後/問題80
上部消化管X線造影で鎮痙薬を投与する理由はどれか。2つ選べ。
1.胃泡を消失させる。
2.胃の蠕動を抑制する。
3.胃液の分泌を抑制する。
4.造影剤による副作用を予防する。
5.硫酸バリウムの粘稠度を低下させる。
午後/問題81
24時間後に追加撮影が行われることがあるのはどれか。
1.食道造影
2.冠動脈造影
3.内視鏡的逆行性胆管膵管造影
4.逆行性尿道造影
5.子宮卵管造影
午後/問題82
造影CT後の三次元処理画像を別に示す。画像処理はどれか。
1.最小値投影法
2.最大値投影法
3.多断面変換表示法
4.ワイヤーフレーム法
5.ボリュームレンダリング法

午後/問題83
右足のX線写真を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.距骨
2.踵骨
3.楔状骨
4.舟状骨
5.立方骨

午後/問題84
上部消化管X線造影検査後の腹部立位X線写真を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.空腸
2.回腸
3.結腸
4.盲腸
5.十二指腸

午後/問題85
上部消化管X線造影写真を別に示す。考えられるのはどれか。
1.潰瘍
2.進行癌
3.ポリープ
4.慢性胃炎
5.粘膜下腫瘍

午後/問題86
腹部CT冠状断像を別に示す。背側から腹側に向かって3番目の画像はどれか。
1.ア
2.イ
3.ウ
4.エ
5.オ

午後/問題87
頭部CT像を別に示す。考えられるのはどれか。
1.脳炎
2.髄膜炎
3.硬膜下血腫
4.硬膜外血腫
5.くも膜下出血

午後/問題88
増感紙-フィルム系を用いて20段のアルミニウムステップウェッジを撮影した。同一撮影条件における2回照射と1回照射のグラフから特性曲線を作成した場合、相対線量の対数値1.5に対応する写真濃度はどれか。
ただし、log10(2) = 0.3とする。

1.0.5
2.1.0
3.1.5
4.2.5
5.3.5
午後/問題89
C-Dダイアグラムを作成する際、使用するのはどれか。
1.ラダーファントム
2.ワイヤファントム
3.バーガーファントム
4.ハウレットチャート
5.ランドルト環チャート
午後/問題90
DR系におけるMTFで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.位置不変性が成立する。
2.エッジ像のESFをフーリエ変換してMTFを求める。
3.プリサンプリングMTFはエリアシングの影響を含まない。
4.スリット像の線像強度分布からフーリエ変換してMTFを求める。
5.オーバーオールMTFはデジタルMTFとディスプレイMTFの和である。
午後/問題91
自己相関関数をフーリエ変換して得られるのはどれか。
1.WS
2.MTF
3.PTF
4.ROC
5.RMS
午後/問題92
信号のある画像をS、雑音のみの画像をNとし、観察者の判定で「信号あり」をS、「信号なし」をNとするとき、ROC解析の刺激-反応行列で正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、PX|xは条件付確率である。
1.P(S|s)を感度という。
2.P(N|s)を特異度という。
3.P(S|n)をヒットという。
4.P(N|n)を真陰性率という。
5.P(N|s) + P(S|s)は1を超える。
午後/問題93
放射線診療従事者の放射線防護体系に対する考え方の順序で正しいのはどれか。
1.防護の最適化 → 個人の線量限度 → 行為の正当化
2.防護の最適化 → 行為の正当化 → 個人の線量限度
3.行為の正当化 → 防護の最適化 → 個人の線量限度
4.行為の正当化 → 個人の線量限度 → 防護の最適化
5.個人の線量限度 → 防護の最適化 → 行為の正当化
午後/問題94
組織荷重係数(ICRP2007年勧告)が0.1を超えるのはどれか。2つ選べ。
1.肺
2.食道
3.乳房
4.甲状腺
5.唾液腺
午後/問題95
診療放射線技師法で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.医師の指示の下に、放射性同位元素を人体内に挿入することができる。
2.免許を取り消された者は、10日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
3.医師または歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
4.免許証を失い、再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、旧免許証を30日以内に厚生労働大臣に返納しなければならない。
5.多数の者の健康診断を一時に行う場合、100万電子ボルト未満のエックス線を照射するときは、医師の立会いを必要としない。
午後/問題96
医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造設備基準はどれか。2つ選べ。
1.人が常時出入りする出入口は1か所とする。
2.エックス線診療室である旨を示す標識を付す。
3.主要構造部は耐火構造とする。
4.エックス線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設ける。
5.画壁の外側を人が通行する可能性がある場合は、画壁の遮へい能力を0.1mSv/週以下とする。
午後/問題97
131Iを37MBq投与された直後の患者と1mの距離で1時間同席した場合、同席者の被ばく線量(μSv)に最も近い値はどれか。
ただし、1m線量当量率定数は0.065μSv・m²・MBq⁻¹・h⁻¹とする。
1.0.3
2.0.6
3.1.2
4.2.4
5.4.8
午後/問題98
放射線診療従事者の線量限度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.実効線量 ― 20mSv/年
2.女子の実効線量 ― 5mSv/月
3.皮膚の等価線量 ― 500mSv/年
4.眼の水晶体の等価線量 ― 150mSv/年
5.緊急作業における実効線量 ― 100mSv
午後/問題99
測定機器と測定対象の組合せで正しいのはどれか。
1.レムカウンタ ― 排液中の放射性同位元素濃度
2.フリッケ線量計 ― 個人被ばく線量
3.個体飛跡検出器 ― 排気中の放射性同位元素濃度
4.GMサーベイメータ ― 作業台の表面汚染密度
5.ハンドフットクロスモニタ ― 管理区域内の空間線量率
午後/問題100
等価線量を算出するのに必要なのはどれか。2つ選べ。
1.組織重量
2.線質係数
3.組織荷重係数
4.放射線荷重係数
5.組織の平均吸収線量
午後/問題101
表面汚染の管理で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.傷口の汚染は直ちに温流水で洗い流す。
2.体内摂取防止には乾式除染が有効である。
3.皮膚の除染には消毒用エタノールを用いる。
4.表面汚染の検出にはスミア法が有効である。
5.表面密度限度の1/10分の1以下であれば管理区域外へ持ち出してよい。
午後/問題102
公衆被ばくとみなされるのはどれか。
1.ジェット機のパイロットの被ばく
2.放射線業務従事者の胎児の被ばく
3.X線撮影された患者の介助者の被ばく
4.X線を用いた臨床研究の志願者の被ばく
5.放射性同位元素を利用する研究者の被ばく
次の問題へ>> 午前問題(98問)

<<前の問題へ 午前/問題(98問)