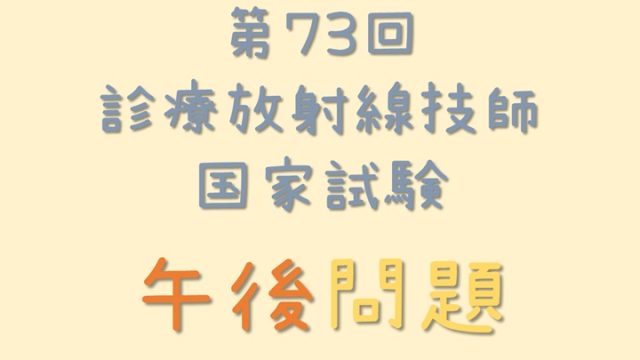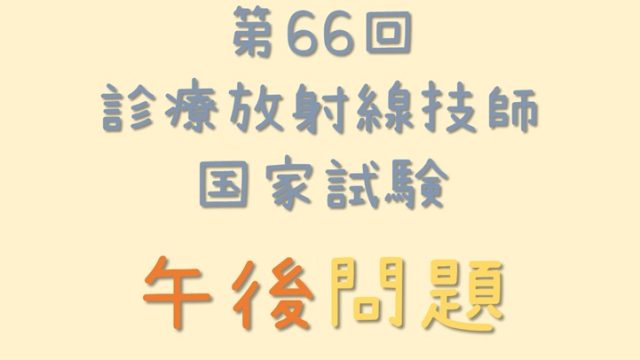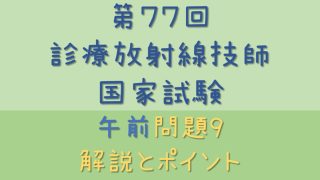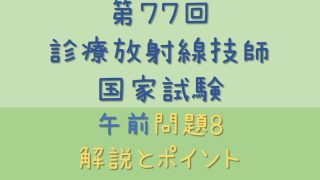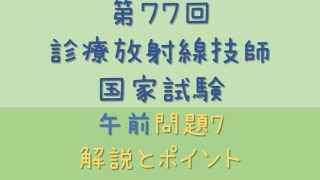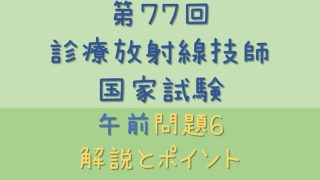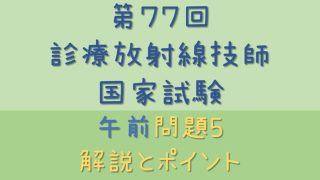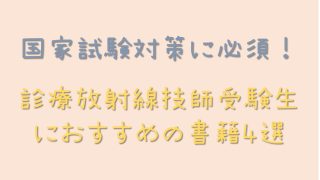午後/問題1
移行上皮で覆われているのはどれか。
1.胸膜
2.血管
3.心膜
4.尿管
5.肺胞
午後/問題2
ATP合成を行うのはどれか。
1.小胞体
2.ゴルジ体
3.リソソーム
4.リボソーム
5.ミトコンドリア
午後/問題3
免疫担当細胞の分化に関与するのはどれか。2つ選べ。
1.胸腺
2.骨髄
3.副腎
4.下垂体
5.甲状腺
午後/問題4
胸骨体部に最も近い位置にあるのはどれか。
1.右心室
2.奇静脈
3.左心室
4.左心房
5.上大静脈
午後/問題5
健常人の心臓の動きで正しいのはどれか。
1.三尖弁の閉鎖時に僧帽弁は開く。
2.大動脈弁の開放時に僧帽弁は閉じる。
3.大動脈弁の閉鎖時に肺動脈弁は開く。
4.左心房の収縮時に右心房は拡張する。
5.左心室の収縮時に右心室は拡張する。
午後/問題6
体液の速度が最も遅いのはどれか。
1.胸管
2.門脈
3.肺静脈
4.肺動脈
5.海綿静脈洞
午後/問題7
胃液の作用でないのはどれか。
1.食物の殺菌
2.脂肪の分解
3.胃粘膜の保護
4.蛋白質の分解
5.炭水化物の分解
午後/問題8
食後の血中糖濃度が最も高いのはどれか。
1.門脈
2.肺静脈
3.肺動脈
4.脾静脈
5.内頸動脈
午後/問題9
体表から3番目の深部にあるのはどれか。
1.硬膜
2.軟膜
3.くも膜
4.側頭動脈
5.硬膜静脈洞
午後/問題10
生理的状態で脳細胞がエネルギー産生に主に利用するのはどれか。
1.乳酸
2.脂肪酸
3.アミノ酸
4.ブドウ糖
5.トリグリセリド
午後/問題11
副腎皮質から分泌されるのはどれか。2つ選べ。
1.グルカゴン
2.アドレナリン
3.エストロゲン
4.コルチゾール
5.アルドステロン
午後/問題12
外分泌機能と内分泌機能とを有するのはどれか。
1.肝
2.膵
3.胸腺
4.顎下腺
5.前立腺
午後/問題13
日和見感染の生じやすい基礎疾患はどれか。
1.髄膜腫
2.白血病
3.高尿酸血症
4.大動脈解離
5.甲状腺機能亢進症
午後/問題14
良性腫瘍はどれか。2つ選べ。
1.骨髄腫
2.脂肪腫
3.線維腫
4.神経芽腫
5.Hodgkinリンパ腫
午後/問題15
癌と腫瘍マーカーの組合せで誤っているのはどれか。
1.大腸癌 ーーーーー CEA
2.絨毛癌 ーーーーー hCG
3.卵巣癌 ーーーーー CA125
4.肝細胞癌 ーーーーー PIVKA-Ⅱ
5.子宮体癌 ーーーーー SCC
午後/問題16
自己免疫疾患でないのはどれか。
1.強皮症
2.多発性筋炎
3.関節リウマチ
4.黄色肉芽腫性胆囊炎
5.Sjögren(シェーグレン)症候群
午後/問題17
骨粗鬆症の原因でないのはどれか。
1.加齢
2.閉経
3.甲状腺機能低下症
4.副甲状腺機能亢進症
5.Cushing(クッシング)症候群
午後/問題18
前縦隔に発生する頻度が高いのはどれか。2つ選べ。
1.胸腺腫
2.奇形腫
3.中皮腫
4.神経腫
5.サルコイドーシス
午後/問題19
アスベストばく露と関係の深いのはどれか。
1.中皮腫
2.肺結核
3.関節リウマチ
4.サルコイドーシス
5.全身性エリテマトーデス
午後/問題20
肺血流が増加するのはどれか。2つ選べ。
1.僧帽弁狭窄症
2.心房中隔欠損症
3.心室中隔欠損症
4.肺動脈弁狭窄症
5.大動脈弁狭窄症
午後/問題21
X線透過性結石はどれか。2つ選べ。
1.尿酸
2.シスチン
3.リン酸カルシウム
4.シュウ酸カルシウム
5.リン酸マグネシウムアンモニウム
午後/問題22
脳出血の好発部位はどれか。2つ選べ。
1.視床
2.小脳
3.脳弓
4.脳梁
5.松果体
午後/問題23
高血圧を生じるのはどれか。
1.膵癌
2.くる病
3.褐色細胞腫
4.前立腺肥大症
5.Parkinson(パーキンソン)病
午後/問題24
男性よりも女性で罹患頻度が高いのはどれか。
1.血友病
2.食道癌
3.心筋梗塞
4.脳血管性認知症
5.Basedow(バセドウ)病
午後/問題25
死亡率が近年減少傾向にあるのはどれか。2つ選べ。
1.胃癌
2.乳癌
3.肺癌
4.大腸癌
5.子宮頸癌
午後/問題26
医療法に基づき都道府県が策定する医療計画の事業でないのはどれか。
1.救急医療
2.災害医療
3.高齢者医療
4.へき地医療
5.周産期医療
午後/問題27
生活習慣病でないのはどれか。
1.高血圧
2.心臓病
3.糖尿病
4.肺線維症
5.脂質異常症
午後/問題28
健康増進法に基づくがん検診で対象年齢が20歳以上なのはどれか。
1.胃癌
2.乳癌
3.肺癌
4.大腸癌
5.子宮頸癌
午後/問題29
経皮的血管形成術の適応でないのはどれか。
1.冠動脈狭窄症
2.腎血管性高血圧症
3.閉塞性動脈硬化症
4.下肢深部静脈血栓症
5.肝部下大静脈狭窄症
午後/問題30
二次救命処置はどれか。
1.下顎挙上
2.胸骨圧迫
3.人工呼吸
4.気管切開
5.脈拍チェック
午後/問題31
X線による生成物で生体への影響が最も大きいのはどれか。
1.陰電子
2.陽電子
3.水素原子
4.酸素原子
5.水酸化ラジカル
午後/問題32
放射線がDNAに与える損傷で誤っているのはどれか。
1.塩基損傷
2.架橋形成
3.一本鎖切断
4.二本鎖切断
5.ヌクレオチド除去
午後/問題33
α/βが小さいのはどれか。2つ選べ。
1.粘膜炎
2.皮膚炎
3.神経障害
4.骨髄抑制
5.筋肉萎縮
午後/問題34
1Gyの全身被ばくで減少が最も遅いのはどれか。
1.単球
2.血小板
3.好中球
4.赤血球
5.リンパ球
午後/問題35
人体に摂取されたときに肺癌を発症するリスクが最も高いのはどれか。
1.²²²Rn
2.²⁰³Hg
3.¹³⁷Cs
4.⁹⁹mTc
5.⁴⁰K
午後/問題36
放射線による発がんとの関連性が最も低いのはどれか。
1.乳癌
2.肺癌
3.白血病
4.上咽頭癌
5.甲状腺癌
午後/問題37
胎児被ばくによる奇形のしきい線量mGyに最も近いのはどれか。
1.0.1
2.1
3.10
4.100
5.1000
午後/問題38
細胞にγ線を10Gy照射する場合、1回で照射するより、5Gyずつ2回に分割して12時間の間隔をおいて照射した方が細胞生存率は高くなる。この現象はどれか。
1.回復
2.増感
3.再増殖
4.再分布
5.再酸素化
午後/問題39
¹⁰B(n, α)⁷Liの反応を用いる治療の生物学的効果で正しいのはどれか。
1.回復が小さい。
2.⁷Liには治療効果がない。
3.正常組織の障害が大きい。
4.多分割照射が有効である。
5.低酸素細胞増感剤が有用である。
午後/問題40
放射線のLETとRBEで正しいのはどれか。
1.電子線は高LET放射線である。
2.RBEには評価法による差はない。
3.LETが高いほどRBEは低下する。
4.高LET放射線では酸素効果比が小さい。
5.高LET放射線では細胞周期依存性が大きい。
午後/問題41
連続エネルギースペクトルを示すのはどれか。2つ選べ。
1.β線
2.消滅光子
3.制動X線
4.オージェ電子
5.内部転換電子
午後/問題42
基底状態にある¹⁰Neのp軌道に配置される電子数はどれか。
1.2
2.4
3.6
4.8
5.10
午後/問題43
半減期 T1/2 の放射性同位元素が N 個存在する場合の放射能はどれか。

午後/問題44
陽子線照射で生成される放射性同位元素はどれか。2つ選べ。
1.¹¹C
2.¹⁴C
3.¹⁸F
4.⁶⁰Co
5.¹⁹²Ir
午後/問題45
X線の発生で正しいのはどれか。
1.制動X線の最短波長は管電圧に比例する。
2.X線の発生強度は管電圧の4乗に比例する。
3.特性X線のエネルギーは管電圧に依存する。
4.エネルギーフルエンスは管電圧波形に依存しない。
5.特性X線の発生は入射電子のエネルギーに依存しない。
午後/問題46
光子エネルギーに対する水の質量エネルギー吸収係数の変化を図に示す。水へのエネルギー付与が最大となるエネルギー(MeV)はどれか。

1.0.01
2.0.05
3.0.1
4.0.5
5.1.0
午後/問題47
密度1.2g/cm³のアクリル樹脂中で最大飛程が5cmである電子線のエネルギー(MeV)はどれか。
1.2.4
2.3.9
3.4.7
4.6.7
5.8.0
午後/問題48
重荷電粒子と物質との相互作用で正しいのはどれか。
1.飛程の最後で速度が大きくなる。
2.励起により大きく方向を変える。
3.阻止能は速度の2乗に反比例する。
4.真空中でチェレンコフ光を発する。
5.エネルギーが同一のα線と陽子線は同じ飛程である。
午後/問題49
中性子による核反応で誤っているのはどれか。
1.⁶Li(n, α)³H
2.²³Na(n, γ)²⁴Na
3.⁵⁴Fe(n, np)⁵³Mn
4.⁵⁹Co(n, 2n)⁶⁰Co
5.²³⁵U(n, f)¹³⁷Cs
午後/問題50
線減弱係数が0.258cm⁻¹である組織のHounsfield値(CT値)はどれか。
ただし、水の線減弱係数は0.215cm⁻¹とする。
1.43
2.120
3.200
4.258
5.430
午後/問題51
X線管に100mAの電流を0.5秒間流した。流れた電子の総数はどれか。
ただし、電子の電荷は 1.6×10−19C とする。
1.3.1×1017
2.1.2×1018
3.3.1×1020
4.6.2×1020
5.1.2×1021
午後/問題52
抵抗10Ωと20Ωの並列回路に電圧10Vの直流電源を接続し30分間通電したときの消費電力量(Wh)はどれか。
1.5.6
2.10
3.11.1
4.25
5.45
午後/問題53
正弦波交流電圧を観測した図を示す。正しいのはどれか。2つ選べ。
ただし、垂直感度は10V/目盛、掃引時間は5ms/目盛とする。

1.最大値は約5Vである。
2.実効値は約35Vである。
3.周期は約6.3msである。
4.平均値は約1.6Vである。
5.周波数は約16Hzである。
午後/問題54
R=20kΩ、L=200mH、C=20pFのR-L-Cの直列共振回路がある。コイルのインダクタンスを一定のまま共振周波数を2倍にするとき、コンデンサの静電容量(pF)はどれか。
1.5
2.10
3.20
4.40
5.80
午後/問題55
電磁気による人体への影響で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.低周波電磁波の急性影響には白内障がある。
2.高周波電磁波の急性影響には神経刺激がある。
3.電磁界によって人体内部に発生する電流は誘導電流である。
4.電磁界によって単位質量当たりに吸収された電力は比吸収率である。
5.電磁界の非接地導電体に接地された人体が接触した点を介して流れる電流は接地電流である。
午後/問題56
導体で正しいのはどれか。
1.琥珀は半導体である。
2.銀は鉄よりも抵抗率が大きい。
3.金属導体の電気抵抗は断面積に比例する。
4.半導体は温度上昇によって抵抗値が低下する。
5.単体の金属導体は温度上昇によって抵抗値が低下する。
午後/問題57
演算増幅回路を図示し、その入力波形を図に示す。入力波形をV₁、V₂に入力したときの出力波形はどれか。


午後/問題58
物理量と放射線の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.W値 ーーーーー 光子
2.カーマ ーーーーー 中性子
3.阻止能 ーーーーー 中性子
4.照射線量 ーーーーー 荷電粒子
5.質量エネルギー吸収係数 ーーーーー 光子
午後/問題59
カーマを表す式はどれか。
ただし、光子のエネルギーを E、フルエンスを Φ、物質の質量エネルギー転移係数を μtr/ρ とする。

午後/問題60
媒質 m 中の小さな空洞内の気体 g 中に単位質量当たり M [C/kg] の電離電荷が生じたとき、媒質 m の吸収線量 Dm [Gy] はどれか。
ただし、気体に対する媒質の質量衝突阻止能比を (Scol/ρ)m,g、気体のW値を W [eV]、素電荷を e [C] とする。

午後/問題61
統計誤差3%の測定値Aと統計誤差4%の測定値Bから得られる値 A−B の統計誤差(%)はどれか。
1.1
2.3.5
3.5
4.7
5.12
午後/問題62
電離箱線量計について正しいのはどれか。2つ選べ。
1.一定強度のX線照射では気圧が高くなると電離電荷は増加する。
2.一定強度のX線照射では気温が高くなると電離電荷は増加する。
3.平行平板形電離箱は円筒形電離箱に比べて一般的に極性効果が小さい。
4.パルス当たりの線量率が高くなるほどイオン再結合の割合は減少する。
5.同じ線量率では連続放射線はパルス放射線に比べてイオン再結合損失が少ない。
午後/問題63
放射線検出器とその特性の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.電離箱線量計 ーーーーー 増幅作用
2.半導体検出器 ーーーーー エネルギー依存性
3.蛍光ガラス線量計 ーーーーー 加熱特性
4.熱ルミネセンス線量計 ーーーーー 紫外線照射
5.ガフクロミックフィルム ーーーーー 着色
午後/問題64
線量で正しいのはどれか。
1.照射線量の単位はA/kgである。
2.照射線量はX線、γ線に定義される。
3.吸収線量は非電離放射線に定義される。
4.等価線量は吸収線量に組織加重係数を乗じたものである。
5.実効線量は等価線量に放射線加重係数を乗じたものである。
午後/問題65
α線放出核種の放射能測定に適した検出器はどれか。
1.外挿電離箱
2.イメージングプレート
3.表面障壁半導体検出器
4.NaI井戸形シンチレータ
5.πガスフロー比例計数管
午後/問題66
エネルギースペクトルで正しいのはどれか。
1.⁹⁰Srのβ線は線スペクトルである。
2.²⁴¹Amのα線は線スペクトルである。
3.⁶⁰Coのγ線は連続スペクトルである。
4.リニアック治療装置のX線は線スペクトルである。
5.拡大ブラッグピーク内の陽子線は線スペクトルである。
午後/問題67
電子線を照射した場合の水中深さによる電離箱線量計の表示値の変化を図に示す。この電子線のエネルギー(MeV)はどれか。
ただし、水に対する質量阻止能は1.9MeV cm²/gとする。

1.6
2.8
3.10
4.12
5.14
午後/問題68
画像検査時の診療放射線技師の対応で適切なのはどれか。
1.X線造影剤を投与するために静脈を刺した。
2.マンモグラフィの際に圧迫板で乳房を圧迫した。
3.胸部X線撮影の際に義歯を外すように指示した。
4.血管造影検査の際にインフォームドコンセントを実施した。
5.腰椎X線撮影の際に患者氏名の確認を撮影終了後に行った。
午後/問題69
ある撮影部位に対し撮影距離 D1、管電流 I1 で撮影したとき適切な撮影線量が得られた。撮影距離を D2 に変化させたとき、適切な撮影線量となる管電流 I2 を求める式はどれか。

午後/問題70
X線撮影で患者被ばく線量が低減するのはどれか。
ただし、他の条件は一定とする。
1.照射野を広げる。
2.管電圧を低くする。
3.管電流を大きくする。
4.付加フィルタを挿入する。
5.焦点-被写体間距離を短くする。
午後/問題71
頸椎撮影の体位と観察目的の組合せで正しいのはどれか。
1.正面撮影 ーーーーー 環軸関節
2.側面中間位撮影 ーーーーー 椎間孔
3.側面前屈位撮影 ーーーーー ドッグライン
4.斜位撮影 ーーーーー 環椎歯突起間距離
5.開口位撮影 ーーーーー 第1~第2頸椎
午後/問題72
胸部正面X線写真における心胸郭比(CTR)で正しいのはどれか。
1.立位撮影より臥位撮影の方が小さい。
2.グリッド比を大きくすると小さくなる。
3.遠距離撮影より近距離撮影の方が小さい。
4.小焦点使用より大焦点使用の方が小さい。
5.腹背方向撮影より背腹方向撮影の方が小さい。
午後/問題73
大骨頸部の側面像が観察される撮影法はどれか。
1.マルチウス法
2.アントンセン法
3.ストライカー法
4.ローゼンバーグ法
5.ラウエンシュタイン法
午後/問題74
足部の正面X線写真で観察できるのはどれか。
1.Y線
2.シェントン線
3.ショパール関節
4.オンブレダン線
5.ハーフムーンサイン
午後/問題75
血管撮影をシングルプレーンからバイプレーンにすることによって低減可能なのはどれか。
1.被ばく線量
2.X線管負荷
3.画像データ量
4.造影剤投与量
5.アーチファクト
午後/問題76
X線CTの撮影で正しいのはどれか。
1.管電圧が高くなるほど画像ノイズは低下する。
2.管電流が大きくなるほど画像ノイズは増大する。
3.ピッチが大きくなるほど被ばく線量は増加する。
4.管電流が大きくなるほど低コントラスト分解能は低下する。
5.スライス厚が厚くなるほど高コントラスト分解能は向上する。
午後/問題77
X線CTで正しいのはどれか。
1.急性膵炎の診断に有用である。
2.造影CTでは検査前日から絶飲食とする。
3.脂肪肝のCT値は脾臓のCT値よりも高い。
4.脳内の出血巣は脳実質よりも低い吸収域を呈する。
5.腹部CTでは造影剤として硫酸バリウムを経口投与する。
午後/問題78
骨塩定量検査法と測定部位の組合せで正しいのはどれか。
1.定量的CT(QCT法) ーーーーー 踵骨
2.定量的超音波(QUS法) ーーーーー 大腿骨
3.X線写真濃度測定(RA法) ーーーーー 頸椎
4.単一エネルギーX線吸収測定(SXA法) ーーーーー 肩関節
5.二重エネルギーX線吸収測定(DXA法) ーーーーー 腰椎
午後/問題79
副鼻腔の正面X線写真別冊No. 1を別に示す。正しい組合せはどれか。
1.ア ーーーーー 軸椎
2.イ ーーーーー 篩骨洞
3.ウ ーーーーー 上顎洞
4.エ ーーーーー 内耳道
5.オ ーーーーー 蝶形骨洞

午後/問題80
脳血管造影の正面写真別冊No. 2を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.外頸動脈
2.椎骨動脈
3.内頸動脈
4.後大脳動脈
5.中大脳動脈

午後/問題81
上部消化管造影写真別冊No. 3を別に示す。正しいのはどれか。
1.前壁が描出されている。
2.背臥位で撮影されている。
3.頭高位で撮影されている。
4.充盈法で撮影されている。
5.噴門部から穹窿部が描出されている。

午後/問題82
下顎骨レベルのCT像別冊No. 4を別に示す。正しい組合せはどれか。
1.ア ーーーーー 喉頭蓋
2.イ ーーーーー 甲状軟骨
3.ウ ーーーーー 耳下腺
4.エ ーーーーー 総頸動脈
5.オ ーーーーー 頸長筋

午後/問題83
肩甲部軟部腫瘤のCT像別冊No. 5を別に示す。考えられるのはどれか。
1.脂肪腫
2.線維腫
3.神経腫
4.リンパ管腫
5.海綿状血管腫

午後/問題84
乳房X線写真別冊No. 6を別に示す。所見で正しいのはどれか。
1.脂肪性乳腺である。
2.構築の乱れを認める。
3.良性石灰化を認める。
4.リンパ節腫大を認める。
5.境界明瞭な腫瘤像を認める。

午後/問題85
胸部X線写真別冊No. 7を別に示す。認められる所見はどれか。
1.左気胸
2.右肺の炎症
3.左乳房の欠損
4.左肺の肺気腫
5.両側肺門の腫大

午後/問題86
腹部X線写真別冊No. 8を別に示す。描出されているのはどれか。
1.異物
2.胆石
3.ニボー
4.尿管結石
5.腹部大動脈の石灰化

午後/問題87
黄疸を主訴とする腹部造影CT写真別冊No. 9を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.胆管
2.門脈
3.肝静脈
4.肝動脈
5.リンパ管

午後/問題88
X線画像特性を調べるファントム画像別冊No. 10を別に示す。評価結果として得られるのはどれか。
1.MTF
2.特性曲線
3.ROC曲線
4.C-Dダイアグラム
5.ウィナースペクトル

午後/問題89
ノイズ特性で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.光量子ノイズを固定ノイズと呼ぶ。
2.NNPSはノイズ量を空間周波数ごとに示す。
3.X線量が少なければざらつきの多い画像となる。
4.RMS粒状度の値が大きいほど粒状性が良いことを示す。
5.デジタルWSの値が大きいほど粒状性が良いことを示す。
午後/問題90
X線画像の評価で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.MTF評価には10 cycles/mmが用いられる。
2.被写体のコントラストが上昇すれば解像力は低下する。
3.ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。
4.RMS粒状度はフィルム濃度のバラツキを標準偏差値で表している。
5.並列細線法で分離不能になった細線の幅をdとすると解像力は 1/(3d) cycles/mm である。
午後/問題91
ROC解析で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.FROC曲線の横軸はFPFである。
2.ROC曲線下の面積 AzA_zAz の最大値は0.5である。
3.LROC解析は信号の有無と位置も認知させる解析法である。
4.平均ROC曲線に差があれば統計的有意差検定は不要である。
5.正常100例のうち70例を正常と判断した時の特異度は70%である。
午後/問題92
DQEで正しいのはどれか。
1.視覚特性が評価できる。
2.理論的な最大値は1となる。
3.高空間周波数ほど高い値となる。
4.CR画像とFPD画像の比較はできない。
5.DQEの値が等しいとき物理的評価は等しい。
午後/問題93
放射線防護体系の三原則に合致しないのはどれか。
1.肺癌が疑われる患者に胸部造影CTを施行する。
2.X線CTで自動曝射コントロール(AEC)を用いる。
3.肝囊胞の経時変化を3か月ごとにX線CTで評価する。
4.放射線部看護師の被ばく線量をガラスバッジで管理する。
5.検診目的の胸部CTでは通常診療より低いX線管電流を用いる。
午後/問題94
放射線診療従事者の線量限度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.実効線量 ーーーーー 20 mSv/年
2.緊急作業に係る実効線量 ーーーーー 100 mSv
3.女子の実効線量 ーーーーー 5 mSv/月
4.眼の水晶体の等価線量 ーーーーー 300 mSv/年
5.妊娠中である女子の腹部表面等価線量 ーーーーー 出産までの期間10 mSv
午後/問題95
ICRPの2007年勧告で組織加重係数が最も小さいのはどれか。
1.肺
2.脳
3.結腸
4.生殖腺
5.赤色骨髄
午後/問題96
放射線被ばくで誤っているのはどれか。
1.放射性ヨードによる内部被ばくは甲状腺に生じる。
2.ラドンガスによる主な被ばくは外部被ばくである。
3.外部被ばく線量は線源からの距離の2乗に反比例する。
4.β線による外部被ばくの遮へいは数mm厚のアルミ板で可能である。
5.体内に取り込まれた放射性物質の有効半減期は物理的半減期より短くなる。
午後/問題97
診療放射線技師法で正しいのはどれか。
1.治療目的で超音波を照射できる。
2.「放射線」にはマイクロ波が含まれる。
3.放射性同位元素を人体内に挿入して照射できる。
4.放射線を照射できるのは病院または診療所に限定される。
5.放射線照射の具体的な指示は医師または歯科医師が行う。
午後/問題98
医療法におけるエックス線装置の届出で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.エックス線装置は定格電流により規制される。
2.同型の装置に更新する場合は届出が不要である。
3.エックス線装置の届出は使用開始後10日以内に行う。
4.エックス線障害の防止に関する構造設備の概要を記載する。
5.エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師または診療エックス線技師の氏名を記載する。
午後/問題99
電離放射線障害防止規則に規定される健康診断で正しいのはどれか。
1.結果は年間30年間の保存義務がある。
2.問診は医師により必要と認められた時に行う。
3.電離放射線健康診断個人票を作成し管理する。
4.前年度20mSvを超えなかった場合は省略できる。
5.管理区域に立ち入った後は1年以内ごとに1回行う。
午後/問題100
表面汚染をサーベイメータ(窓面積12cm²法)で測定したとき、総計数率が3000cpm、自然計数率が25cpmであった。表面汚染密度(Bq/cm²)に最も近い値はどれか。
ただし、換算係数は20とする。
1.0.21
2.12.4
3.82.6
4.833
5.4958
午後/問題101
放射性同位元素による表面汚染で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.ふき取り面積は10cm²である。
2.固着性汚染の場合はスミア法を用いる。
3.α線を放出する核種の汚染密度限度は4Bq/cm²である。
4.β線を放出する核種の汚染密度限度は40Bq/cm²である。
5.表面が浸透性の材質ではふき取り効率が非浸透性よりも高い。
午後/問題102
放射線事故時の対応で応急措置の原則に含まれないのはどれか。
1.通報
2.安全保持
3.安全教育
4.拡大防止
5.過大評価
次の問題へ>> 午前問題(98問)
第66回診療放射線技師国家試験 | 午前問題(98問)第66回診療放射線技師国家試験 | 午前問題(98問)に関する解説記事です。...
<<前の問題へ 午前/問題(98問)
第65回診療放射線技師国家試験 | 午前問題(98問)第65回診療放射線技師国家試験 | 午後問題(102問)に関する解説記事です。...