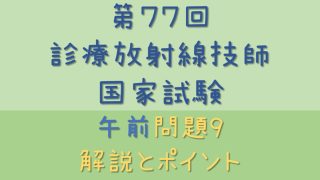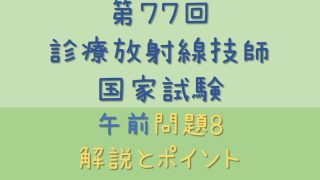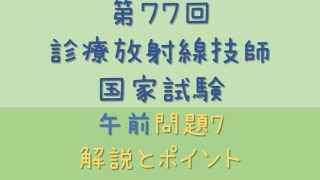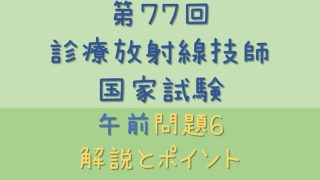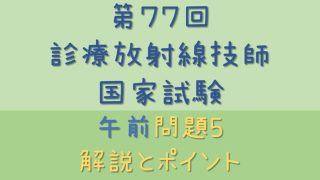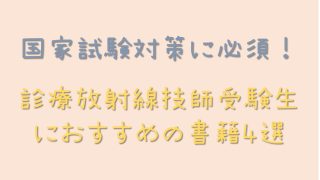午後/問題1
炭素の同位体で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.11C は天然に存在する。
2.13C は天然に存在する。
3.11C は安定同位元素である。
4.13C は放射性同位元素である。
5.14C は年代測定に利用される。
午後/問題2
原子炉で製造される核種はどれか。2つ選べ。
1.67Ga
2.99Mo
3.123I
4.131I
5.201Tl
午後/問題3
PET薬剤の放射化学的純度の検定に用いるのはどれか。
1.ホットアトム法
2.クロラミン-T法
3.トリチウムガス接触法
4.高速液体クロマトグラフィ
5.ラクトパーオキシダーゼ法
午後/問題4
放射化分析で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.検出感度が高い。
2.成分定量の精度が高い。
3.自己遮へいの影響がない。
4.使用する装置が安価である。
5.多元素同時分析が可能である。
午後/問題5
回転陽極X線管の短時間許容負荷が増加するのはどれか。2つ選べ。
1.回転数を増やす。
2.陽極半径を大きくする。
3.ターゲット角を大きくする。
4.フィラメント電流を大きくする。
5.ターゲット-フィラメント間距離を広げる。
午後/問題6
X線用可動絞りで最もX線管側にある部品はどれか。
1.上羽根
2.奥羽根
3.下羽根
4.ミラー
5.目盛板
午後/問題7
X線自動露出制御装置を用いた撮影で画像濃度が低下するのはどれか。
1.被写体厚の増加
2.撮影時間の短縮
3.後面検出方式における管電圧の低下
4.前面検出方式における管電圧の上昇
5.後面検出方式における管電流の増大
午後/問題8
撮像管と比較した場合のCCDの特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.振動に弱い。
2.残像が多い。
3.変調度が低い。
4.画像歪みが少ない。
5.ダイナミックレンジが広い。
午後/問題9
X線透視撮影装置で正しいのはどれか。
1.近接式は術者のX線防護が不要である。
2.近接式は遠隔式に比べ術者被ばくが少ない。
3.近接式は遠隔式に比べ正確な体位変換が困難である。
4.アンダーテーブルX線管形はオーバーテーブルX線管形に比べ術者の被ばくは少ない。
5.オーバーテーブルX線管形はアンダーテーブルX線管形に比べ患者の体位変換が困難である。
午後/問題10
散乱線除去グリッドで正しいのはどれか。
1.同一のグリッドであれば管電圧が低いほど露出倍数は小さい。
2.グリッド比は吸収はくの間隔に対する吸収はくの高さの比である。
3.グリッド密度とは中心部における10cm当たりのはくの本数をいう。
4.グリッド密度が同じであればグリッド比が大きいほど露出倍数は小さい。
5.グリッド比が同じであればグリッド密度が小さいほど露出倍数は小さい。
午後/問題11
MRIで用いられるフェーズドアレイコイルの特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.送受信型コイルである。
2.複数のコイルで構成されている。
3.コイルから離れた部位のSN比が高い。
4.小さなFOVでの高解像度撮影に用いられる。
5.パラレルイメージングを行う際に使用される。
午後/問題12
無散瞳眼底カメラによる検査のとき、眼球に最も近いところに位置する部品はどれか。
1.有孔ミラー
2.対物レンズ
3.ハロゲンランプ
4.フォーカシングレンズ
5.クイックリターンミラー
午後/問題13
超音波検査で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.体内での音速は空気中よりも速い。
2.周波数が高いほど深部での観察領域が広い。
3.カラードップラーでは探触子に近づく血流を青で表示する。
4.コンベックス式探触子では振動子が直線上に配列されている。
5.深部の減衰を補正するために感度補正(STC)の調整が必要である。
午後/問題14
X線CT装置の日常点検項目に含まれないのはどれか。
1.ノイズ
2.スライス厚
3.幾何学的歪み
4.コントラストスケール
5.高コントラスト分解能
午後/問題15
STIR法で正しいのはどれか。
1.CHESS法よりSN比は高い。
2.最初に90度のRFパルスを印加する。
3.水と脂肪の位相差を利用した撮影法である。
4.脂肪の縦磁化がゼロになる時間にTEを設定する。
5.CHESS法より磁場の不均一性の影響を受けにくい。
午後/問題16
SE法を用いたMRCPで正しいのはどれか。
1.水抑制画像である。
2.短いTEで撮影される。
3.最大値投影法が有用である。
4.脊椎が高信号で描出される。
5.陽性造影剤を経口投与する。
午後/問題17
MRIのアーチファクトで正しいのはどれか。
1.磁化率アーチファクトはTEを長くすることで軽減できる。
2.モーションアーチファクトは動きの方向に一致して出現する。
3.化学シフトアーチファクトは静磁場強度が高いほど大きくなる。
4.折り返しアーチファクトはスライス厚を薄くすることで回避できる。
5.トランケーションアーチファクトは分解能を低く設定すると抑制できる。
午後/問題18
超音波用造影剤に含まれるのはどれか。
1.空気
2.ヨウ素
3.トリウム
4.ガドリニウム
5.硫酸バリウム
午後/問題19
探触子を第4肋間胸骨左縁から頭側に傾けるようにして撮影した心エコーの四腔断面像(four chamber view)別冊No. 1を別に示す。矢印で示す構造はどれか。
1.右心房
2.僧帽弁
3.三尖弁
4.心尖部
5.心室中隔

午後/問題20
無散瞳眼底写真撮影で正しいのはどれか。
1.検査は明室で実施する。
2.撮影前に散瞳剤を点眼する。
3.色覚異常の診断に有用である。
4.視神経乳頭は鼻側に位置する。
5.ピント合わせの照明に紫外線を使用する。
午後/問題21
頭部MRIのT2強調像別冊No. 2を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.海馬
2.視床
3.中脳
4.脳梁
5.尾状核

午後/問題22
MRIのT2強調矢状断像別冊No. 3を別に示す。正しい組合せはどれか。2つ選べ。
1.ア ーーーーー 鼻腔
2.イ ーーーーー 脳脊髄液
3.ウ ーーーーー 上咽頭
4.エ ーーーーー 横突起
5.オ ーーーーー 第11胸椎

午後/問題23
健常成人のMRCP像別冊No. 4を別に示す。矢印で示す構造はどれか。
1.右肝管
2.総肝管
3.胆囊管
4.総胆管
5.主膵管

午後/問題24
右季肋部斜走査の腹部超音波像別冊No. 5を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.膵管
2.門脈
3.肝静脈
4.総肝管
5.脾静脈

午後/問題25
ポジトロン放射性薬剤と検査目的の組合せで正しいのはどれか。
1.13N-NH3 ーーーーー 悪性腫瘍の転移巣検索
2.15O-CO ーーーーー 脳腫瘍の再発診断
3.15O-CO2 ーーーーー 脳酸素代謝量測定
4.15O-O2 ーーーーー 心筋血流量測定
5.18F-FDG ーーーーー 難治性部分てんかんの焦点検索
午後/問題26
得られる像が拡大するコリメータはどれか。2つ選べ。
1.平行多孔
2.ピンホール
3.コンバージング
4.スラントホール
5.ダイバージング
午後/問題27
SPECTの分解能に影響しないのはどれか。
1.回転半径
2.散乱補正
3.画像再構成法
4.放射能減衰補正
5.収集マトリクスサイズ
午後/問題28
18F-FDG PETのSUV値で正しいのはどれか。
1.血糖値が高いと腫瘍で高くなる。
2.運動後に検査をすると筋肉で低くなる。
3.皮下への注射漏れがあると脳で高くなる。
4.投与から時間経過すると腫瘍で一定となる。
5.18F-FDGが体外に排出されず体内に均等に分布すると1になる。
午後/問題29
SPECTの画像処理で正しいのはどれか。
1.Wiener フィルタでスムージングがかかる。
2.Sorenson 法は再構成後のデータを補正する。
3.Chang 法は再構成前の投影データを補正する。
4.Butterworth フィルタは低域通過フィルタである。
5.Ramachandran フィルタは高周波成分を低減する。
午後/問題30
脳血流SPECT像別冊No. 6を別に示す。矢印で示す構造はどれか。
1.視床
2.小脳
3.中脳
4.側頭葉
5.線条体

午後/問題31
甲状腺中毒症となっている時期に甲状腺の123Iの集積がびまん性に増加するのはどれか。
1.亜急性甲状腺炎
2.無痛性甲状腺炎
3.外因性甲状腺中毒症
4.Basedow(バセドウ病)
5.Plummer(プランマー病)
午後/問題32
肝胆道シンチグラフィで正しいのはどれか。
1.99mTc-GSAを使用する。
2.投与後15分以内で撮影が完了する。
3.心臓と肝臓のカウント比を計測する。
4.乳児肝炎と胆道閉鎖症の鑑別に使用する。
5.酸刺激に対する放射性医薬品の排泄を評価する。
午後/問題33
腎臓の核医学検査で正しいのはどれか。
1.腎動態シンチグラフィでは側面像で解析する。
2.99mTc-DTPAシンチグラフィでは腎血漿流量を算出できる。
3.99mTc-DMSAシンチグラフィは腎瘢痕の評価に有用である。
4.腎動態シンチグラフィの検査前に患者の水分摂取を制限する。
5.99mTc-DMSAシンチグラフィは腎機能が低下している患者には禁忌である。
午後/問題34
18F-FDGの集積性が低いのはどれか。
1.大腸癌
2.悪性黒色腫
3.悪性リンパ腫
4.頭頸部平上皮癌
5.高分化型肝細胞癌
午後/問題35
病期診断にTNM分類が用いられるのはどれか。2つ選べ。
1.脳腫瘍
2.舌癌
3.食道癌
4.多発性骨髄腫
5.悪性リンパ腫
午後/問題36
抗悪性腫瘍薬との同時併用で放射線治療が行われるのはどれか。2つ選べ。
1.膠芽腫
2.甲状腺癌
3.肺癌
4.肝臓癌
5.骨肉腫
午後/問題37
定位放射線治療(SRT)で誤っているのはどれか。
1.数回までの分割照射で行う。
2.画像誘導放射線治療(IGRT)と組み合わせて行う。
3.強度変調放射線治療(IMRT)と組み合わせて行う。
4.頭頸部腫瘍では照射中心位置精度の許容範囲は1mm以下である。
5.体幹部腫瘍では照射中心位置精度の許容範囲は10mm以下である。
午後/問題38
強度変調放射線治療(IMRT)における投与線量の不確かさの要因のうち、放射線治療計画装置と関係ないのはどれか。
1.不均質補正
2.ビームモデリング
3.線量計算アルゴリズム
4.低MU時のビーム特性
5.CT値-電子密度変換テーブル
午後/問題39
6MVリニアックのX線で正しいのはどれか。
1.線量最大深は2cmである。
2.線量指標TPR20,10は0.5である。
3.平均エネルギーは3MeVである。
4.連続エネルギースペクトルをもつ。
5.水との主な相互作用は光電効果である。
午後/問題40
乳房温存療法で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.接線照射を行う。
2.10MVのX線を使用する。
3.照射野前縁に乳頭を含めない。
4.断端陽性部への電子線追加照射をする。
5.標準的な線量時間配分は70Gy/35分割/週である。
午後/問題41
陽子線の照射野形成で正しいのはどれか。
1.患者ボーラスは照射方向ごとに異なる。
2.Wobbler(ワブラー)電磁石には直流電源を用いる。
3.スキャニング法のビーム利用効率は散乱体法より悪い。
4.レンジシフターで拡大ブラッグピーク(SOBP)を形成する。
5.二重散乱体法の第2散乱体は一種類の材質からできている。
午後/問題42
前立腺癌の根治的外部照射で最も可能性の高い晩期障害はどれか。
1.貧血
2.腎不全
3.直腸出血
4.脊髄麻痺
5.萎縮性膀胱
午後/問題43
放射線治療の適応となるのはどれか。2つ選べ。
1.子宮筋腫
2.卵巣囊腫
3.網膜剝離
4.甲状腺眼症
5.真性ケロイド
午後/問題44
放射線治療に伴う晩期障害で直列臓器はどれか。
1.唾液腺
2.肺
3.肝臓
4.脊髄
5.骨髄
午後/問題45
論理回路を図に示す。対応する論理演算式はどれか。

午後/問題46
相反則不軌に基づく写真現象はどれか。
1.隣接効果
2.圧力効果
3.間欠効果
4.クロスオーバ効果
5.Russell(ラッセル)効果
午後/問題47
画像Aと空間フィルタFを図に示す。画像Aに対してFのフィルタで処理したときの画素値 aij(i=3,j=3)で正しいのはどれか。

1.−2
2.−1
3.0
4.1
5.2
午後/問題48
階調処理はどれか。2つ選べ。
1.ボケマスク処理
2.メディアンフィルタ処理
3.ヒストグラム平坦化処理
4.リージョングローイング
5.ダイナミックレンジ圧縮処理
午後/問題49
放射線情報システムの機能に含まれないのはどれか。
1.照射録の作成
2.検査の予約管理
3.患者基本情報の登録
4.検査の実施情報入力
5.モダリティとの情報連携
午後/問題50
生体を構成する元素で最も割合が少ないのはどれか。
1.H
2.C
3.N
4.O
5.Ca
午後/問題51
不要物質の分解処理に関わる細胞小器官はどれか。
1.Golgi(ゴルジ)装置
2.中心体
3.ミトコンドリア
4.リソソーム
5.リボゾーム
午後/問題52
形質細胞に分化して抗体を産生するのはどれか。
1.B細胞
2.T細胞
3.好酸球
4.好中球
5.マクロファージ
午後/問題53
声帯が付着する構造で声帯の前方に位置するのはどれか。
1.甲状軟骨
2.喉頭蓋
3.舌骨
4.披裂軟骨
5.輪状軟骨
午後/問題54
リンパ系について正しいのはどれか。
1.胸管は右の静脈角に注ぐ。
2.胸管の起始部を脈絡叢という。
3.胸管は上半身のリンパ液を集める。
4.右下半身のリンパ液は左の静脈角に注ぐ。
5.静脈角とは肩甲上静脈と鎖骨下静脈の合流部をいう。
午後/問題55
腎臓で血液のろ過を行うのはどれか。
1.糸球体
2.腎盂
3.腎静脈
4.尿管
5.尿細管
午後/問題56
顔面の知覚を伝達するのはどれか。
1.滑車神経
2.三叉神経
3.外転神経
4.顔面神経
5.迷走神経
午後/問題57
音が伝わる順序で正しいのはどれか。
1.鼓膜 → 耳管 → 蝸牛 → 聴神経
2.鼓膜 → 耳管 → 三半規管 → 聴神経
3.鼓膜 → 耳管 → 耳小骨 → 聴神経
4.鼓膜 → 耳小骨 → 蝸牛 → 聴神経
5.鼓膜 → 耳小骨 → 三半規管 → 聴神経
午後/問題58
骨転移の頻度が低いのはどれか。
1.腎癌
2.乳癌
3.肺癌
4.食道癌
5.前立腺癌
午後/問題59
肺塞栓症と関係が深いのはどれか。
1.肺気腫
2.動脈硬化
3.心房細動
4.僧帽弁狭窄症
5.深部静脈血栓症
午後/問題60
好発年齢が乳児期なのはどれか。
1.急性虫垂炎
2.十二指腸潰瘍
3.潰瘍性大腸炎
4.肥厚性幽門狭窄症
5.Crohn(クローン)病
午後/問題61
ホルモン分泌低下による疾患はどれか。
1.先端巨大症
2.中枢性尿崩症
3.原発性アルドステロン症
4.Cushing(クッシング)症候群
5.Parkinson(パーキンソン)病
午後/問題62
非ステロイド性抗炎症薬の作用はどれか。2つ選べ。
1.解熱
2.抗菌
3.鎮痛
4.粘膜保護
5.気管支拡張
午後/問題63
動脈化学塞栓療法(TACE)が最も多く行われるのはどれか。
1.肺癌
2.食道癌
3.肝細胞癌
4.前立腺癌
5.子宮体癌
午後/問題64
罹患率が日本よりも欧米で高いのはどれか。2つ選べ。
1.胃癌
2.結核
3.前立腺癌
4.肝細胞癌
5.Crohn(クローン)病
午後/問題65
分子に間接作用するのはどれか。2つ選べ。
1.・H
2.・OH
3.システイン
4.グルタチオン
5.システアミン
午後/問題66
X線に対する反応のα/βが最も小さいのはどれか。
1.脱毛
2.下痢
3.脊髄症
4.口内炎
5.湿性落屑
午後/問題67
5Gyの全身被ばくの、2か月後に生じるのはどれか。
1.発がん
2.腸管死
3.骨髄死
4.分裂死
5.中枢神経死
午後/問題68
多分割照射で正しいのはどれか。
1.晩期有害事象の頻度が高い。
2.分裂頻度の高い腫瘍に有用である。
3.照射間隔は6時間以内が望ましい。
4.化学療法との同時併用は禁忌である。
5.転移性骨腫瘍の症状緩和に用いられる。
午後/問題69
LETで誤っているのはどれか。
1.LETが高いとOERも高い。
2.炭素線は陽子線よりLETが高い。
3.中性子線はX線よりLETが高い。
4.単位としてkeV/μmが用いられる。
5.低LET放射線では感受性が細胞周期に依存する。
午後/問題70
核子個当たりの平均結合エネルギーが最も大きいのはどれか。
1.4He
2.12C
3.24Mg
4.56Fe
5.226Ra
午後/問題71
制動X線で正しいのはどれか。
1.第2半価層は第1半価層より厚い。
2.実効エネルギーは線質表示に用いられる。
3.最短波長はターゲットの原子番号で決まる。
4.発生効率はターゲットの原子番号に反比例する。
5.エネルギー分布はMoseley(モーズレー)の法則に従う。
午後/問題72
光子と物質との相互作用で正しいのはどれか。
1.電子対生成のしきいエネルギーは1.022MeVである。
2.電子対生成で生じる電子と陽電子の運動エネルギーは等しい。
3.三電子生成のしきいエネルギーは1.533MeVである。
4.三電子生成では2個の電子と2個の陽電子が生成される。
5.三電子生成は原子核のCoulomb(クーロン)場との相互作用によって起きる。
午後/問題73
重荷電粒子と物質との相互作用で正しいのはどれか。
1.α線はβ線より比電離が小さい。
2.衝突阻止能は速度の二乗に比例する。
3.衝突損失能より放射損失能が大きい。
4.空気中での比電離は飛程中一定である。
5.速度が光速を超えるとCherenkov(チェレンコフ)光を発する。
午後/問題74
核磁気共鳴現象において、90度RFパルス印加後に300msで縦磁化が50%まで回復する組織の縦緩和時間(ms)はどれか。
ただし、loge2 = 0.693とする。
1.111
2.150
3.189
4.433
5.600
午後/問題75
磁束密度の単位で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.Wb
2.A・m−1
3.Wb・m−2
4.N・A−1
5.N・A−1・m−1
午後/問題76
図の回路で、100μFのコンデンサCを4.8Vに充電した後、スイッチSを閉じた。
時間が無限に経過する間に抵抗Rを流れる電子数(個)はどれか。

1.3×106
2.3×109
3.3×1012
4.3×1015
5.3×1021
午後/問題77
Viを入力信号、Voを出力信号としたときの回路を図に示す。リミッタ回路はどれか。
ただし、Rは抵抗、Cはコンデンサ、D1及びD2はダイオード、V1及びV2は基準電圧とする。

1.A
2.B
3.C
4.D
5.E
午後/問題78
二極真空管のフィラメントに一定電流を流した後に陽極電圧を上昇させたときの特性曲線を図に示す。正しいのはどれか。

1.A
2.B
3.C
4.D
5.E
午後/問題79
吸収線量Dを表す式はどれか。
ただし、Eは光子のエネルギー、Φはフルエンス、μtr/ρは物質の質量エネルギー転移係数、μen/ρは物質の質量エネルギー吸収係数、μ/ρは物質の質量減弱係数とする。

午後/問題80
放射線検出器と関係する項目の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.BF3計数管 ーーーーー 熱中性子線
2.半導体検出器 ーーーーー イオン再結合
3.電離箱線量計 ーーーーー 電子なだれ
4.蛍光ガラス線量計 ーーーーー 紫外線照射
5.ラジオクロミックフィルム ーーーーー 現像
午後/問題81
ある放射性試料の計数は1分間測定で800カウント、バックグラウンドが10分間測定で400カウントであった。
正味計数率(cpm)とその標準偏差はどれか。
1.120 ± 3
2.120 ± 6
3.120 ± 12
4.160 ± 15
5.160 ± 18
午後/問題82
電離箱線量計を用いた高エネルギーX線の線量計測で必要ない補正項目はどれか。
1.温度
2.極性効果
3.線量率依存性
4.イオン再結合
5.エネルギー依存性
午後/問題83
1.37及び2.75MeVのγ線を放出する24Naのエネルギースペクトルを測定した結果、0.51MeVにピークが観測された。
このピークを説明する現象はどれか。
1.後方散乱
2.制動放射
3.干渉性散乱
4.電子対生成
5.コンプトン散乱
午後/問題84
X線撮影における解剖学的説明で正しいのはどれか。
1.肋骨弓の下縁は第2腰椎の高さにある。
2.体を左右に二分する面を冠状面という。
3.乳様突起はOMラインよりも頭側に位置する。
4.四肢を体の正中線に近づける動きを外転という。
5.第1足趾と踵骨先端を結ぶ線は足部を撮影する際の基準線となる。
午後/問題85
血管造影検査における術者の被ばくで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.プロテクタの内側と外側に線量計を装着する。
2.実効線量限度は年間につき100mSvである。
3.甲状腺を防護するためにネックガードを装着する。
4.患者の体格が大きくなるほど術者の被ばくは減る。
5.被ばくの主要因はX線管からの漏洩X線である。
午後/問題86
立位および坐位が困難な消化管穿孔を疑う患者に対する腹部単純X線撮影法で正しいのはどれか。
1.背臥位腹背方向撮影
2.背臥位右斜位撮影
3.腹臥位背腹方向撮影
4.左側臥位腹背方向撮影
5.右側臥位左右方向撮影
午後/問題87
濃度が20%(w/v)の硫酸バリウム懸濁液を3,000mL作成するために必要な硫酸バリウム粉末の重量(g)はどれか。
1.30
2.60
3.300
4.600
5.6,000
午後/問題88
CTコロノグラフィで正しいのはどれか。
1.骨盤高位で撮影する。
2.油性ヨード造影剤を使用する。
3.二酸化炭素で大腸を拡張させる。
4.大腸内部の色調観察が可能である。
5.Fine network patternを描出できる。
午後/問題89
Dose Length Product(DLP)の単位で正しいのはどれか。
1.mGy
2.mSv
3.mGy・cm
4.mSv・cm
5.mSv/cm
午後/問題90
腰椎の正面X線写真別冊No. 7を別に示す。正しい組合せはどれか。
1.ア ーーーーー 肋骨
2.イ ーーーーー 椎弓根
3.ウ ーーーーー 第1腰椎
4.エ ーーーーー 椎間関節
5.オ ーーーーー 下関節突起

午後/問題91
右乳房のX線写真別冊No. 8を別に示す。正しいのはどれか。
1.MLO撮影である。
2.脂肪性乳腺である。
3.リンパ節腫大を認める。
4.辺縁不整な腫瘤像を認める。
5.びまん性に石灰化を認める。

午後/問題92
脳血管のIVRを施行中に撮影した血管造影像別冊No. 9を別に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。
1.DSA画像である。
2.脳底動脈が描出されている。
3.動脈瘤が前大脳動脈にある。
4.動脈瘤をコイル塞栓術で治療している。
5.ガイドワイヤの先端は中大脳動脈にある。

午後/問題93
胸部造影CT像別冊No. 10を別に示す。矢印で示すのはどれか。
1.肺動脈
2.大動脈弓
3.上大静脈
4.上行大動脈
5.下行大動脈

午後/問題94
X線画像系の特性評価用器具の写真別冊No. 11を別に示す。この器具を使用して特性曲線を作成するとき誤差の要因となるのはどれか。2つ選べ。
1.線質硬化
2.散乱X線
3.焦点サイズ
4.器具の厚さの精度
5.空気によるX線の吸収

午後/問題95
値が常に1になるのはどれか。2つ選べ。
ただし、TNFは真陰性率、TPFは真陽性率、FNFは偽陰性率、FPFは偽陽性率とする。
1.TNF + FNF
2.TNF + FPF
3.TNF + TPF
4.TPF + FNF
5.TPF + FPF
午後/問題96
国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告において胎児への確定的影響を考慮すべきしきい線量(mGy)はどれか。
1.1
2.20
3.100
4.650
5.2,500
午後/問題97
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.一般病室内 ーーーーー 1mSv/年
2.病院の敷地の境界 ーーーーー 250μSv/月
3.病院内の人が居住する区域 ーーーーー 1.3mSv/月
4.放射線治療病室の画壁の外側 ーーーーー 1mSv/週
5.診療用放射線照射装置使用室の画壁の外側 ーーーーー 1mSv/週
午後/問題98
等価線量を算出するのに必要なのはどれか。2つ選べ。
1.組織重量
2.線質係数
3.組織加重係数
4.放射線加重係数
5.組織の平均吸収線量
午後/問題99
施設の放射能汚染防止策で誤っているのはどれか。
1.管理区域内での飲食を禁止する。
2.排気フィルタを定期的に交換する。
3.排気口は高い煙突や建物の高層部に設置する。
4.管理区域内の気圧を外気よりわずかに陽圧となるように調節する。
5.排気口から排出する空気中の放射能濃度をガスモニタで監視する。
午後/問題100
198Auグレイン1,500MBqを永久刺入された患者から1mの距離で1時間介助を行う看護師の被ばく線量(μSv)に最も近いのはどれか。
ただし、患者の体内における減弱は考慮しないものとし、実効線量率定数は0.0576μSv・m²・MBq⁻¹・h⁻¹とする。
1.21.6
2.43.2
3.86.4
4.172.8
5.345.6
次の問題へ>> 午前問題(100問)

<<前の問題へ 午前/問題(100問)